
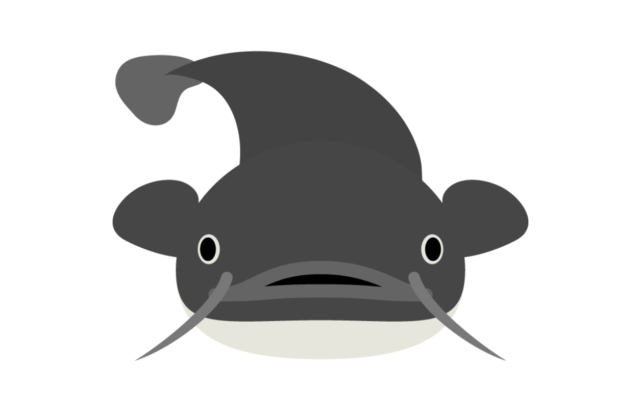
近年、耐震等級についての認知度は高まり、多くの方がその重要性を理解されています。しかし、耐震等級3と耐震等級3相当の違いについては、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。今回は、この2つの違いを解説しながら、福岡で注文住宅を建てる際にどのような選択をすべきかを考えていきます。
まず、耐震等級とは、建物の耐震性能を示す指標であり、1から3の等級があります。数字が大きくなるほど耐震性が向上し、以下のような基準で定められています。
当然ながら、耐震性が高いほうが地震に対する安心感も増します。しかし、耐震等級3を選択する際には、追加費用が発生する場合があり、それを理由に耐震等級2を選ぶ方も少なくありません。
耐震等級は、建築基準法の一部に含まれており、特定行政庁が審査し、認定を行います。また、建築基準法の中には「許容応力度計算」と呼ばれる構造計算の考え方があり、ビルや3階建て以上の建物ではこの計算が必須となります。
耐震等級1、2、3の認定は、行政が建築図面や計算結果を確認し、「この建物は耐震等級3を満たしている」と認定を行うことで成立します。この認定を受けることが、耐震性能の公的なお墨付きとなるのです。
「耐震等級3」と「耐震等級3相当」は、一見同じように見えますが、大きな違いがあります。
✅ 耐震等級3
✅ 耐震等級3相当
計算手法自体は同じですが、認定の有無が異なります。認定を受けていない「耐震等級3相当」の場合、実際の強度が設計通りであるかどうか、第三者による保証がないため注意が必要です。
耐震等級の基準には、「品確法」と「許容応力度計算」の2種類があり、どちらの基準で計算されたかによって、同じ耐震等級3でも強度に差が生じます。
つまり、許容応力度計算に基づいた耐震等級2は、品確法による耐震等級3と同等の強度を持つ場合があるのです。
また、建築基準法の最低基準である耐震等級1についても、安全率が0.75と設定されているため、計算上は耐震等級1を満たしていないケースも存在します。これが、耐震等級1の建物を選択することのリスクにもつながるのです。
耐震性能を選ぶ際に、「コストを抑えたい」「大きな地震はめったに来ない」と考える方も多いでしょう。しかし、安全性を考慮すると、最低でも耐震等級2を選択し、可能であれば許容応力度計算による耐震等級2以上を確保することをおすすめします。
また、「耐震等級3相当」を選ぶ場合は、行政の認定を受けていないため、本当に設計通りの耐震性が確保されているか慎重に判断する必要があります。耐震等級3を取得するための費用がかかることを懸念される方もいますが、命や家族の安全を守るためには、確実な耐震性能を確保することが最も重要です。
ぜひ参考にして、安全な住まいづくりを進めていただければと思います。
追記 耐震性を高めるためには
耐震性を高めるためには、壁や柱の直下率を上げることが重要です。以下に詳しく説明します。
直下率は、1階と2階の柱や耐力壁がどの程度同じ位置に配置されているかを示す指標です。柱の直下率は、2階の柱の下に1階の柱がある割合を示し、壁の直下率は2階の耐震壁の下に1階の耐震壁がある割合を示します。
: 1階と2階で柱の位置が一致する数を2階の柱の数で割った数値です。
柱の直下率=一致する柱の数2階の柱の数×100%
: 1階と2階で耐力壁の位置が一致する長さを2階の耐震壁の長さで割った数値です。
壁の直下率=一致する壁の長さ2階の壁の長さ×100%
直下率を上げることで、建物の耐震性が向上します。具体的には以下のようなメリットがあります。
: 上下階の柱や壁が揃うことで、地震時の力が効率的に伝達され、建物全体のバランスが良くなります。
: 柱の直下率が高いと、梁に掛かる負担が減り、倒壊のリスクが低下します。
: 直下率を高めることで、少ない耐力壁で耐震等級を確保できる可能性があります。
: 50%以上が目安で、理想は60〜70%です。
: 60%以上が推奨されます。
直下率を意識した設計は、建物の耐震性を高める上で非常に重要です。特に、自由設計の注文住宅では、直下率を考慮した設計が求められます。
「注文住宅」に関連する記事
福岡注文住宅の流れ
工務店やハウスメーカーと注文住宅を建てるための土地購入ガイド
注文住宅を建てるなら。工務店やハウスメーカーの選び方と住宅ローンのコツ
住宅購入に必要な諸経費とは?
注文住宅を購入する際の諸経費と登記手続き
注文住宅購入時にかかる諸経費と注意点