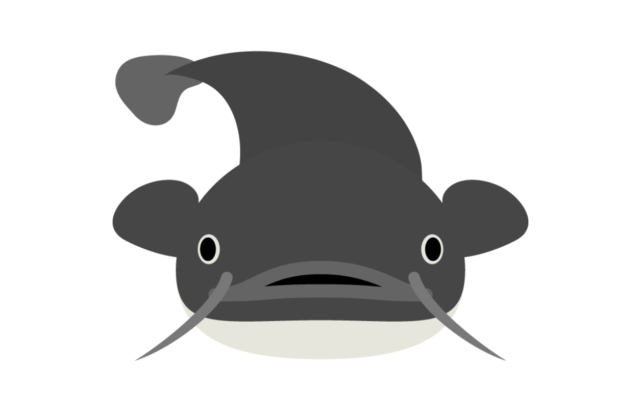
福岡警固断層と住宅建設の安全対策
はじめに
福岡県は日本の中でも比較的地震リスクが低い地域とされていましたが、2005年に発生した福岡県西方沖地震により、活断層の危険性が再認識されました。福岡市の中心部を通る警固断層は、今後も大規模な地震を引き起こす可能性があるため、新築・既存住宅を問わず耐震性を考慮した家づくりが求められます。本稿では、警固断層の詳細と、福岡県で住宅を建てる際の具体的な対策について詳しく解説します。
1. 警固断層とは?
1.1 断層の概要
警固断層(けごだんそう)は、福岡県の博多湾から福岡市を通り、筑紫野市へと伸びる長さ約27kmの活断層で、九州地方で最も地震リスクが高い断層の一つとされています。この断層は、北西の延長線上にある福岡県北西沖の断層と合わせて「警固断層帯」と呼ばれ、全長約55kmに及びます。
1.2 過去の活動と将来のリスク
警固断層の最新の活動は約3,400年から4,300年前とされていますが、将来的な活動の可能性は高いと考えられています。政府の地震調査研究推進本部によると、今後30年以内の地震発生確率は0.3%〜6%とされ、日本国内の活断層の中でも比較的高いリスクを持つグループに属します。
2. 住宅建設における耐震対策
家を建てる際には、警固断層の影響を考慮した耐震設計が不可欠です。以下に、具体的な耐震対策を詳しく説明します。
2.1 耐震等級の選択
日本の建築基準法では、耐震等級1〜3の基準が設けられています。福岡県では、警固断層帯の影響を考慮し、**耐震等級3(最高レベル)**の住宅を選択することが強く推奨されます。耐震等級3の住宅は、建築基準法の1.5倍の耐震性能を持ち、大地震時でも倒壊のリスクを最小限に抑えます。
2.2 耐震構造と制震・免震技術
- 耐震構造: 柱や梁を強化し、地震の揺れに耐える設計。
- 制震技術: ダンパーを利用し、地震のエネルギーを吸収して揺れを抑える。
- 免震技術: 建物の基礎部分に免震装置を導入し、地震の影響を軽減する。
2.3 基礎の強化
- ベタ基礎の採用: 建物全体の荷重を均等に分散し、不同沈下を防ぐ。
- 地盤改良の実施: 軟弱地盤に対しては、地盤改良工事を行い、地震時の建物沈下を防ぐ。
2.4 建築材料の選定
- 木造・鉄筋コンクリート(RC造)の選択: 耐震性に優れた構造を採用。
- 屋根材の軽量化: 瓦屋根よりも金属屋根やスレート材を採用し、建物全体の重量を抑える。
2.5 住宅の間取り設計
- 耐力壁を適切に配置: 地震時に建物がねじれないようバランスよく配置。
- 柱の直下率を上げる。:過分に 2階の柱の直下に1階の柱が乗っていないなど、無理な柱の位置は耐震性を低下させるため、適度な配置を考慮。
3. 既存住宅の耐震補強
3.1 耐震診断の実施
特に1981年(新耐震基準導入前)以前に建築された住宅は、専門家による耐震診断を受けることが重要です。
3.2 耐震補強の方法
- 壁の補強: 筋交いや耐震パネルを追加し、耐震性を向上させる。
- 基礎の補強: 鉄筋コンクリートを増設し、建物の耐久性を強化。
- 屋根の軽量化: 重い瓦屋根を撤去し、軽量な屋根材に変更。
4. 防災対策と日常的な備え
4.1 家具の固定
- 高さのある家具はL字型金具や耐震ジェルを使用して固定。
- 冷蔵庫や食器棚などの大型家電も固定し、転倒を防ぐ。
4.2 感電ブレーカーの設置
- 地震時に自動で電源を遮断し、通電火災を防ぐ。
- 福岡市では一部の自治体が補助金制度を設けている場合もある。
4.3 避難計画の作成
- 家族で避難ルートと集合場所を決めておく。
- 近隣の避難所や防災マップを事前に確認。
5. まとめ
警固断層が引き起こす地震は、福岡県内の多くの地域に大きな影響を与える可能性があります。新築住宅の建設においては、耐震等級3の設計、ベタ基礎、耐震・制震・免震技術の導入が望まれます。また、既存住宅に住む方も、耐震診断や補強を行い、日常的な防災対策を進めることで、地震リスクを大幅に軽減することができます。
これらの対策を講じることで、安全で安心な住まいを実現しましょう。
最新の報道です。 (2025/03/20 OA)  TNCニュース
TNCニュース
ハザードマップについて
文責 監修者 長崎秀人
福岡県の注文住宅専門の設計事務所「長崎材木店一級建築士事務所」の代表。宅建業も営み、業界歴は35年に及び、建築士・宅地建物取引士の資格を持つ。明治30年創業の同社は、設計から施工、不動産取引まで幅広く手掛け、公正なサービス専門性と実績に基づく信頼性の高い情報を提供している。

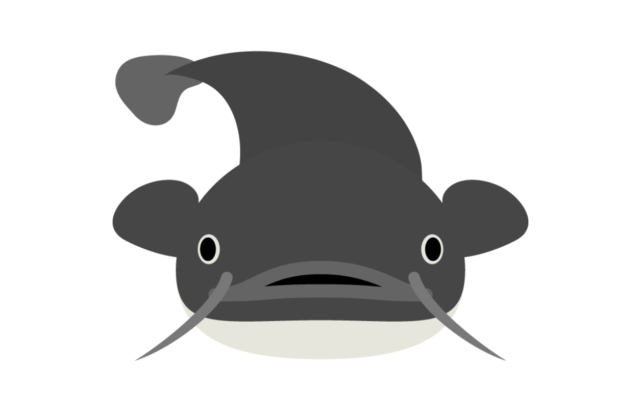
TNCニュース