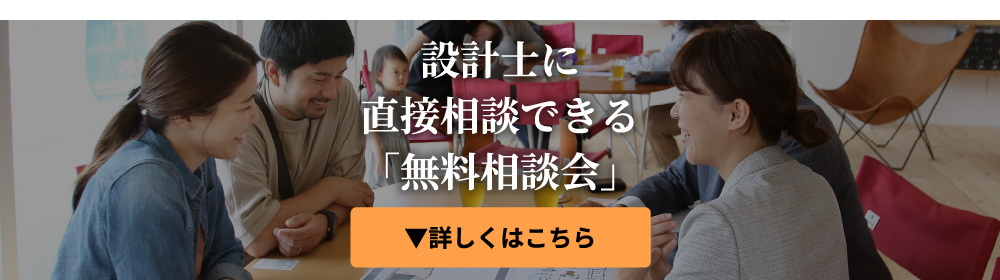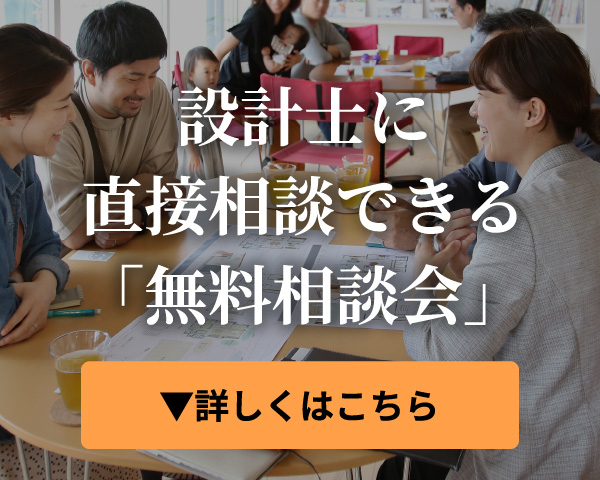『大事なのは想いをどう届けるかにある』
『大事なのは想いをどう届けるかにある』
家をつくるということは、ただの「建築物」を用意することではない。
少なくとも、私たちはそう思っている。
この国に“家”という言葉ができてどれほどの歳月が流れたかは知らないが、
そこには「暮らし」や「家族」や、もう少し言えば、実家という「家族の絆」や「安らぎ」が宿っている。
そういう“目に見えないもの”を形にする仕事なのだと、年を重ねるごとに思い知らされる。
私は設計並びに住宅施工を生業としている。
図面を描き、木を選び、職人と対話し、現場に立つ。
それはどこにでもある仕事かもしれない。
だが、私たちはそれを「商売」ではなく、「役目」だと思ってやっている。
建設業という括りでは、売って建てているものかもしれない。けれど、
“買ってください”と叫ぶのではなく、“この家で人生を謳歌して欲しい”と願っている。
今の世の中には、B to B、B to C、そしてD to Cという言葉がある。
ビジネスの形を示す略語。
簡単に言えば、
-
B to B(Business to Business)とは企業が企業にモノやサービスを売る形。
-
B to C(Business to Consumer)は企業が一般の人に売るスタイル。
-
そして、D to C(Direct to Consumer)は、作り手が直接、生活者に届けるかたち。
たとえば、シャツを作る工場がアパレルブランドに売るのがB to B、
そのブランドが百貨店で客に売るのがB to C。
一方で、職人が自らネットでお客に売る、それがD to C。想いがストレートに伝わる。
どのかたちが正しいとか、間違っているという話ではない。
ただ、D to Cには、他のどのスタイルにもない、切実さと誠実さがある。
私たちのやり方は、D to C(Direct to Consumer)。
D to C――作り手が、使い手に直接手渡す形。決して嘘はつけない。
私たちが設計し、職人とつくり、木を選び、時間をかけて仕上げた住まい。
その家を、私たち自身が、直接、あなたに語りかける。
この床の木は、宮崎県の太陽を浴びて育った飫肥杉です。
この土台は、四万十川のきれいな水で育った四万十檜です。
そこに立って、深く息を吸ってください。きっとわかると思う。
これは、”商品”ではなく、“暮らしの器”です。
D to Cの肝は、間に立つ人やモノをすべて飛び越えて、「想い」を手渡すことにある。
YouTubeで、ブログで、ホームページで。
伝わってほしいと思う。わかってほしいと思う。
「ただの家」ではなく、「その人のための住まい」を、私たちは届けているのだと。
その家がどんな想いで生まれたのか。
どんな木を使い、どんな職人が刻み、何にこだわって作ったのか。
私たち自身が、それを言葉にして、映像にして、声にして届ける。
それは、手紙のようなものだ。
どうして、代表者の私が直接、顔を出して、YouTubeで語るのか?
なぜ、工事中の現場まで動画で案内するのか?
家が建ったあとも、永久保証プログラムなど導入して何年も何十年も付き合い続けるのか?
答えは簡単だ。
これは、売るための仕事じゃない。
「残すための仕事」だからだ。決して嘘はつけない。
ブランドメッセージ 「より美しく、住み継ぐ」
もしこの文を、同じように家を作る誰かが読んでいたら、伝えたいことがある。
D to Cという言葉の意味は、カッコこいいマーケティング用語ではない。
それは、「誰かのために、直接、心を使うこと」だ。
時代は変わった。
「いいものをつくれば売れる」時代は終わった。
「言葉にしなければ伝わらない」時代になった。
私たちは家をつくる。
そして、どうしてこの家をつくったのかを、自分たちの口で伝える。
ブログで。YouTubeで。ホームページで。
これは営業でも、広告でもない。
私たちのスタッフは営業はしていない。想いを伝える仕事をしている。
ひとつの家にこめた“人生の提案”だと思っている。
大量生産でも、FCのような代理販売でもなく。
手間をかけて、言葉を重ねて、顔を出して、声を届ける。
D to Cというのは、
そういう“手ざわり”のある商いのことだ。
それはたぶん、
モノではなく、信頼を届ける仕事。
大手のように年間何百棟何千棟も売ることはできない。
もしこの仕事を「効率の悪いやり方だ」と笑う人がいたら、
私は少し笑ってこう言うだろう。
「でもね、うちは“家”を売ってるんじゃない。“物語の器”を届けてるんだ」って。

 092-942-2745
092-942-2745