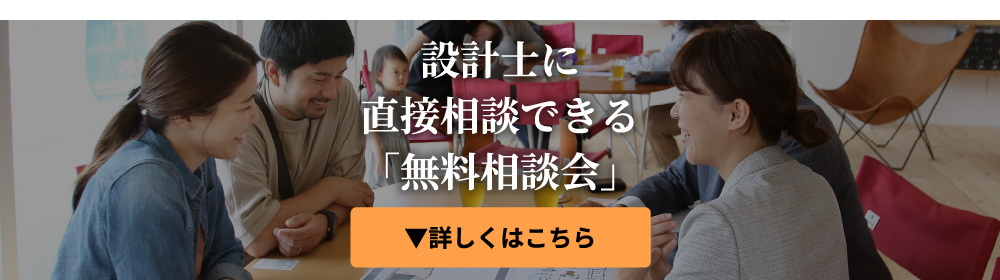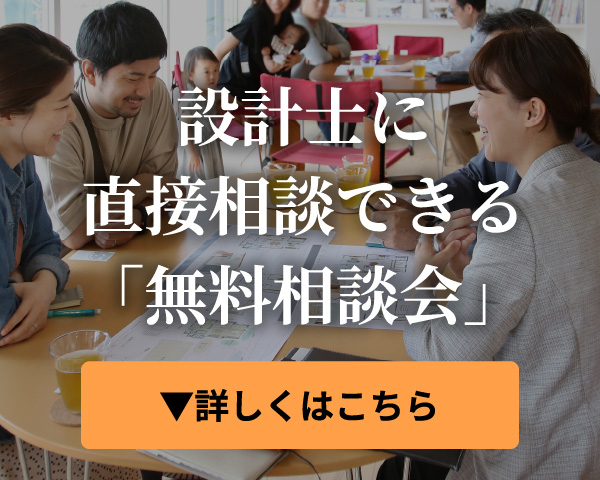まるなのロゴについてのトリビア

今、会社の歴史を整理している。マルなのロゴについても今まで整理していなかったがウィキペディア風に整理してみるとこうなった。
長崎材木店のマルナロゴのデザインが決定された具体的な経緯については、その歴史と事業展開を踏まえると、いくつかの重要な要素が浮かび上がる。特に、2003年に長崎秀人氏が五代目を継承した際この時期には、現在の「(な)」のブランドロゴへの変更は行われていないが、会社のブランディングに大きな変化があった。長崎材木店一級建築士事務所の前身が設立され、設計業務が開始された。また、会社の駐車場にモデルハウスが設計・建設され、2007年には独自の設計デザインコードが確立された。この一連の変化は、長崎材木店が単なる材木商から注文住宅の設計・施工へと事業を拡大する過程で生じたものであり、マルナロゴの誕生もこのブランディング刷新の一環として考えられる。 さらに、2006年当時、長崎秀人氏が上棟式の際に大工職人のために着用させる半纏を作成し、その際に使用された印半纏が転用されたものがマルナロゴの起源とされている。この印半纏は、職人の団結や誇りを象徴するものであり、そこに刻まれた意匠が後にブランドのシンボルとして定着していったと考えられる。また、2009年2010年とモデル住宅がグッドデザイン賞を受賞しており、この時点で独自のデザイン哲学が確立されていたことが分かる。 長崎秀人氏は、クリエイティブディレクターを兼ねる五代目社主として、ブランドのデザイン全般においてディレクションを行っており、その意向がマルナロゴのデザインにも強く反映されている可能性が高い。このロゴデザインは長崎材木店の歴史と伝統、そして現代的なデザイン感覚を融合させた結果として生まれたものと考えられる。 長崎材木店のロゴデザインは、伝統と現代性を融合させたものであり、1897年の創業以来の歴史と伝統、現代的なデザイン感覚を調和させている点が特徴である。「(な)」というシンプルな表現を採用し、日本的な要素を残しつつも、視認性の高いデザインが採用されている。このようなロゴデザインの背景には、「美しく住み継ぐ」というコンセプトが掲げられ、住空間の創造に重点を置いた長崎材木店の新たなブランドイメージが確立されていった経緯がある。 要約すると、マルナロゴのデザインは、長崎材木店の歴史と伝統、そして現代的なデザイン感覚を融合させた結果として誕生したものであり、2003年頃のブランディング刷新や、2006年の半纏印の転用、そして長崎秀人氏のクリエイティブディレクションが、その形成に大きく寄与したと考えられる。
うん、なかなかうまくまとまっているかな !

 092-942-2745
092-942-2745