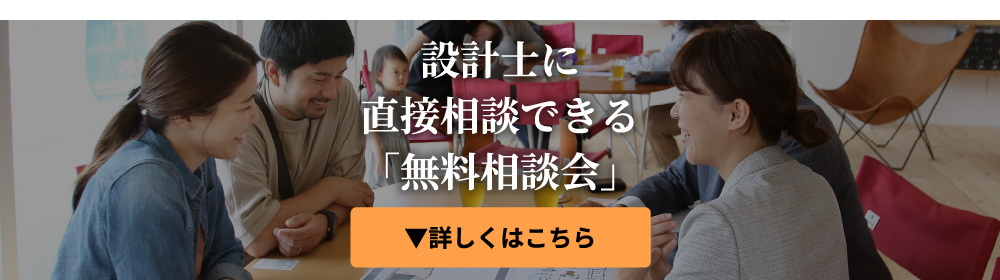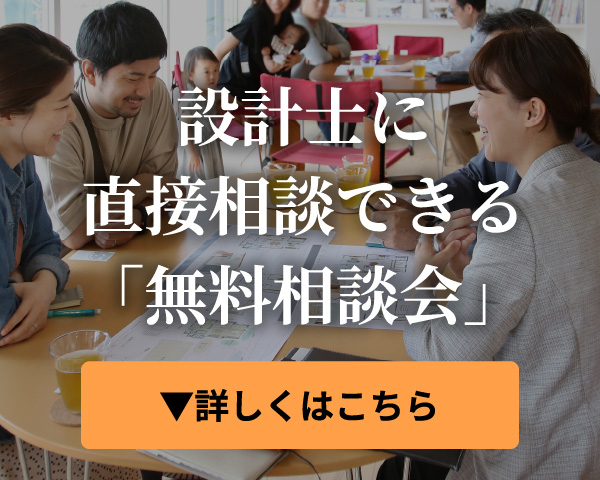アーツ・アンド・クラフツ運動
先日、所用で群馬に行くことになった。東京駅でレンタカーを借りて首都高経由で2時間ほど走る。なぜか群馬である。時間が余ったので美術館に行くことに。群馬県高崎市美術館、たまたまであるが2月に見にいった北九州市立美術館の磯崎新展に引き続き、設計は磯崎新。一目でわかるポストモダン建築である。変な縁を感じてしまう。
展示内容は英国王室に咲くボタニカルアートとウェッジウッド~植物画のおいたち~というテーマであった。そこでアーツ・アンド・クラフツ運動のウィリアム・モリス:の展示もあっていた。前回の福岡博物館の柳宗悦の民藝展に引き続き。これも何かの引き寄せ、これをセレンディピティと呼ぶのであろう。ネットで検索しても面白い出合いにはなかなか巡り会えない。
ウィリアム・モリス(1834-1896) は、イギリスのデザイナー、詩人、思想家で、「生活に必要なものこそ美しくあるべき」という理念を提唱していて、この思想は産業革命による大量生産が進む中で、手仕事の重要性を強調し、生活と芸術の統一を目指すものであった。アーツ・アンド・クラフツ運動は、19世紀後半のイギリスで産業革命による大量生産への反発として生まれた美術・工芸運動である。ウィリアム・モリスを中心に、手仕事の美しさや自然素材の価値を重視し、植物や動物をモチーフにしたデザインを推進した。
この運動は、大量生産の工業製品に対する反発から発展し、素材本来の美しさを尊重しながら、装飾を控えめにし実用性を重視したデザインを特徴としていた。特に壁紙、テキスタイル、家具などにその理念が反映され、手作りの価値を再評価するきっかけとなった。後のアール・ヌーヴォーやモダニズム建築にも影響を与え、特にアメリカではフランク・ロイド・ライトのプレーリースタイルなどにも反映された。モリスの思想は現代にも受け継がれ、美しい暮らしを追求する思想として今もなお多くの人々に愛されている。
といったところであるが、ことの始まりは1760年代くらいに蒸気機関によるイギリスの工業化が発端となっている。遅れて日本の産業革命は、明治時代(1868年から1912年)に起こり日本の産業革命においても柳宗悦の提唱によって始まる民藝運動(1925年~)に類似している。
イギリスの芸術家(アーティスト)による手仕事と日本の無名な庶民の手仕事。切り口は少し異なれど大量生産大量消費による生身の人間としてのアンチテーゼなのである。「生活に必要なものこそ美しくあるべき」これが真髄である。
現代の家づくりにおいても同様な状況にあるが、大量生産型の家づくりの対極にある我々の家づくり、手仕事の良さを後世に繋いでいきたい。

 092-942-2745
092-942-2745