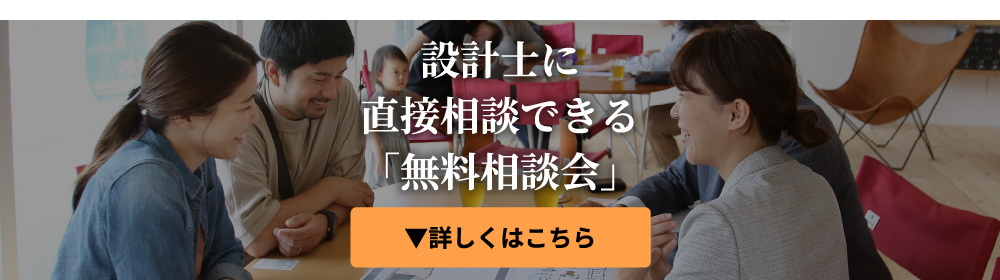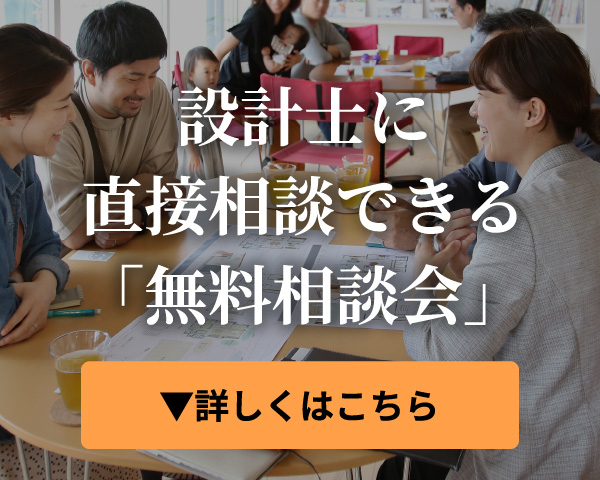静かに、そして確かに、住まいの風景は変わりつつある。
静かに、そして確かに、住まいの風景は変わりつつある。
かつて、日本の住宅設計においてリビングルームの中心にはテレビが据えられることが前提だった。大きなソファはそのテレビに向かい、家族が自然とそこに集うような配置が「理想の間取り」とされてきた。テレビは単なる家電ではなく、家族を一つにまとめる象徴的な存在だった。しかし、時代と共にその役割は変わりつつある。
2015年あたりからスマートフォンやタブレットが普及仕出してきた現代。家族それぞれが個別のデバイスを持ち、それぞれの時間を楽しむ生活スタイルが当たり前になった。これに伴い、「テレビを中心とした間取り」という固定観念もまた解放されつつある。リビングルームは必ずしも「テレビを見るための空間」ではなくなり、むしろ多様な用途や価値観に応じて柔軟に設計されるべき場所になっている。
例えば、深い軒をだした大きな窓から自然光を取り込み、外の景色を楽しめるように椅子やソファを開口部に向けて配置するリビング。あるいは、壁一面を本棚やアートスペースにして、静かに過ごす時間を重視する空間設計。また、リビングそのものを廃してキッチンやダイニングと一体化させることで、家族が自然と集まりやすい動線を作る工夫も増えている。これらはすべて、「画一的な間取り」から脱却し、それぞれのライフスタイルに寄り添った設計思想の表れだ。
建築的には、この変化は非常に興味深いし歓迎したい事である。テレビという「一点」を中心とした空間構成から解放されることで、住まい全体がより多様で有機的なデザインへと進化している。視線の抜けや自然との接続性を重視した間取り、動線の自由度を高めたプランニングなど、新しい時代の暮らし方が建築デザインにも反映されている。
窓際に置かれたゆったりした椅子に腰掛けて外を眺める。その先にはテレビでは決して映し出せない日の移ろいや風に揺れる木々の影が広がっている。その瞬間、人々は気づく。「住まいとは単なる機能性だけでなく、自分自身と向き合う場所でもある」ということを。
テレビから解放されることで生まれる新しい生活様式。それは決して孤立ではなく、新しい形で個人と家族が共存する道なのだと思う。窓越しに見える景色や、リビングで響く家族の笑い声。その中で、それぞれが自分らしく生きる空間。それこそが、これからの住まいづくりで目指すべき姿なのではないだろうか。
リビングルームはもはや「テレビを見る場所」ではない。それは家族それぞれが自由でありながらも繋がり合える場であり、外の景色や自然とも対話できる場所へと進化している。敷地のポテンシャルを最大限読み解く設計。そして、その進化こそが現代住宅設計の新たな挑戦であり、可能性だと言えるだろう。
住まいとは生き方そのものだ。だからこそ、その形は時代と共に変わり続ける。そして私たち設計者は、その変化を受け止め、新しい暮らし方を提案する責任と喜びを背負っている。

 092-942-2745
092-942-2745